あなたは取得しやすくて役に立つ資格はないか探していませんか?世の中には資格や検定試験と呼ばれているものがたくさんありますが、その多くは民間資格であり、取得しても役に立たないなんてことも珍しくありません。そんな中で比較的容易に取得できて役に立つ国家資格「危険物取扱者甲種」について解説します。私もこの資格を活かして現在も医薬品系の工場で仕事をしています。
危険物取扱者甲種とは
危険物取扱者は、消防法に基づき危険物を取り扱うための国家資格です。一定数量以上の危険物を貯蔵または取り扱う事業所や施設では、危険物取扱者の資格保有者を配置することが法律で定められています。危険物取扱者は大きく分けて丙種、乙種、甲種があり、その中でも甲種を取得することで、全ての危険物を取り扱うことができるようになります。ガソリンスタンド、化学工場、製油所、倉庫業、塗料メーカー、運送会社など幅広い業種で評価されています。以下の表で3つの区分の特徴を比較しました。
| 区分 | 取り扱いが可能な危険物 | 特徴 |
|---|---|---|
| 甲種 | 全ての危険物(第1〜6類) | 全ての危険物取り扱い施設において、保安監督者や無資格者の立ち会い者として業務を行うことができる。 |
| 乙種 | 特定の類(第1〜6類)の危険物 | 資格を取得した類の危険物取り扱い施設において、保安監督者や無資格者の立ち会い者として業務を行うことができる。 |
| 丙種 | 特定の危険物 | 出題範囲が最も狭い入門資格。特定の危険物の取り扱い業務を行うことができる。 |
引用:https://www.shouboshiken.or.jp/kikenbutsu/
試験の概要
3つの区分を比較しながら試験の概要を見ていきましょう。
受験資格
| 区分 | 受験資格 |
|---|---|
| 甲種 | 一定の資格が必要(後述) |
| 乙種 | 受験資格なし |
| 丙種 |
引用:https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/annai/qualified.html
受験資格は上の表の通りです。丙種と乙種では資格が不要な一方、甲種では一定の資格が必要になります。
甲種 受験資格1:大学等において化学に関する学科等を修めて卒業した者
・化学に関する学科等の詳細については以下のボタンからご確認ください。
・大学等の詳細については以下の以下のボタンからご確認ください。
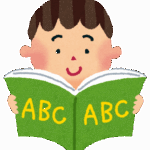
証明書類として卒業証明書、卒業証書、学位記が必要ですが、一般財団法人 消防試験研究センターが定めた化学に関する学科または課程が記載されていないと、証明書として認められないことがあるので気をつけましょう。実際に私も薬学系の修士号を取得したにも関わらず、証明書として認められませんでした。
甲種 受験資格2:大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者
・化学に関する授業科目の詳細については以下のボタンからご確認ください。
・証明書類として、修得単位が明記された単位修得証明書又は成績証明書が必要になります。
甲種 受験資格3:乙種危険物取扱者免状を有する者(実務経験2年以上)
乙種の危険物取扱者免状を取得し、製造所等の事業所で危険物の取り扱い実務を2年以上経験した場合、甲種の受験が可能となります。証明書類として、取得した免状に加えて、実務を経験した事業所から実務経験証明書を取得する必要があります。
甲種 受験資格4:乙種危険物取扱者免状を有する者
乙種の危険物取扱者免状を取得したが実務経験が2年以下の場合、次の4種類以上の免状を交付されている必要があります。
- 第1類または第6類
- 第2類または第4類
- 第3類
- 第5類
甲種 受験資格5:修士・博士の学位を有する者
証明書類として学位記が必要となります。
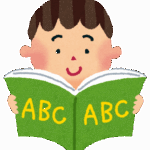
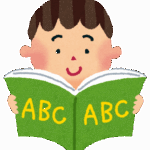
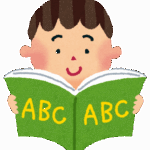
学位記には一般財団法人 消防試験研究センターが定めた化学に関する学科または課程が記載されている必要があるので注意しましょう。
出題範囲と問題数、出題方式、試験時間
出題方式は共通してマーク・カードを使う筆記試験ですが、出題範囲、問題数、試験時間が区分ごとに異なります。
丙種(試験時間:1時間15分、四肢択一式)
| 大問 | 試験科目 | 問題数 |
|---|---|---|
| 1 | 危険物に関する法令 | 10 |
| 2 | 燃焼及び消火に関する基礎知識 | 5 |
| 3 | 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 10 |
引用:https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/annai/subject.html
丙種は3つの区分の中で最も出題範囲が狭く、試験時間が短い試験です。危険物取扱者としての入門資格となっています。
乙種(試験時間:2時間、五肢択一式、)
| 大問 | 試験科目 | 問題数 |
|---|---|---|
| 1 | 危険物に関する法令 | 15 |
| 2 | 基礎的な物理学及び基礎的な化学 | 10 |
| 3 | 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 10 |
引用:https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/annai/subject.html
大問3は受験する類の危険物に限られた出題となります。一方で大問2では物理と化学の基礎が問われるため、物理と化学の初学者は時間をかけた勉強が必要となります。
甲種(試験時間:2時間30分、五肢択一式、)
| 大問 | 試験科目 | 問題数 |
|---|---|---|
| 1 | 危険物に関する法令 | 15 |
| 2 | 物理学及び化学 | 10 |
| 3 | 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 10 |
引用:https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/annai/subject.html
大問3は全ての危険物が出題対象となります。また大問2では物理と化学の応用的な知識も必要となるため、しっかりとした対策が必要となります。
合格基準、合格率
各試験の難易度を合格基準、合格率の観点で比較しました。
| 区分 | 合格率 (R6年度) | 合格基準 |
|---|---|---|
| 甲種 | 35.4% | 各試験科目において正答率が60%以上 |
| 乙種 1類 | 66.8% | |
| 乙種 2類 | 67.0% | |
| 乙種 3類 | 66.0% | |
| 乙種 4類 | 31.7% | |
| 乙種 5類 | 63.6% | |
| 乙種 6類 | 67.4% | |
| 乙種 計 | 38.1% | |
| 丙種 | 49.1% |
・引用1:https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/annai/way.html
・引用2:https://www.shoubo-shiken.or.jp/result/
3つの区分で比較すると、出題範囲の広さから甲種<乙種<丙種の順に合格率が低くなっています。一方で、乙種を細分化すると乙4類が最も合格率が低くなっています。合格率だけで難易度を比較することは難しいですが、出題範囲の広さから勉強時間は甲種が最も必要になると考えられます。
合格までの勉強方法
私が甲種の試験に合格するまでの勉強時間は平均
1日2時間×3ヶ月で約180時間でした。私は薬学系の修士号を持っており化学系の知識をある程度持っていたため、化学の初学者の方に比べて勉強時間は少し短いかもしれません。
使用した教材や勉強の順序について詳しく解説します。
使用教材
1. わかりやすい!甲種危険物取扱者試験
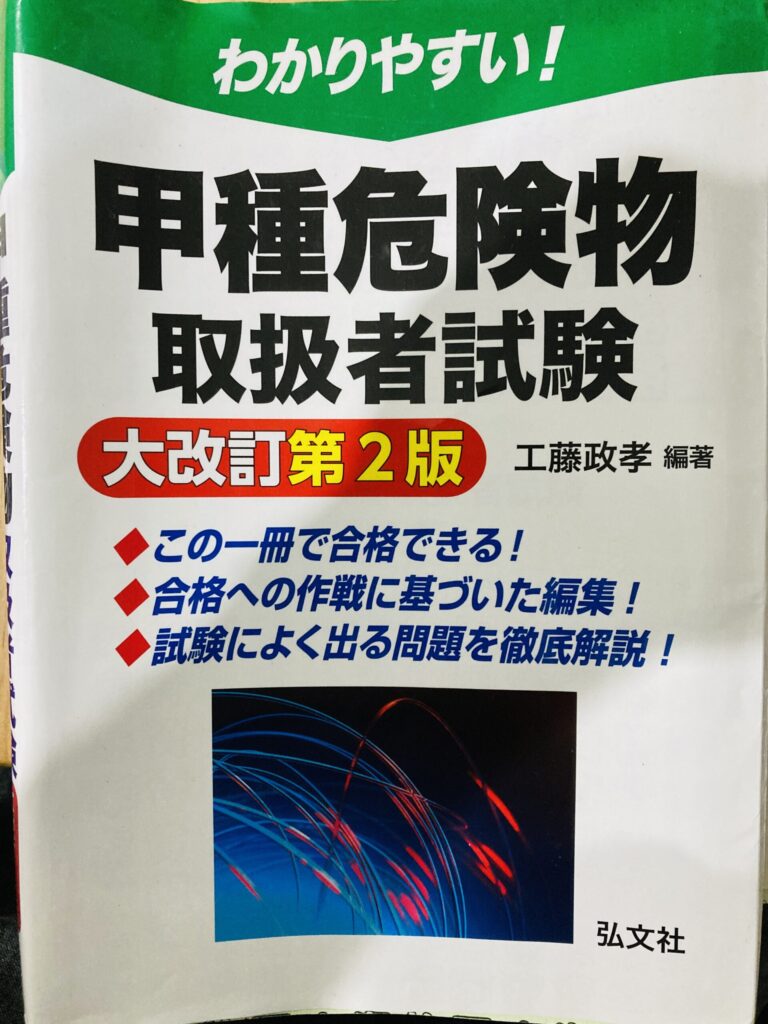
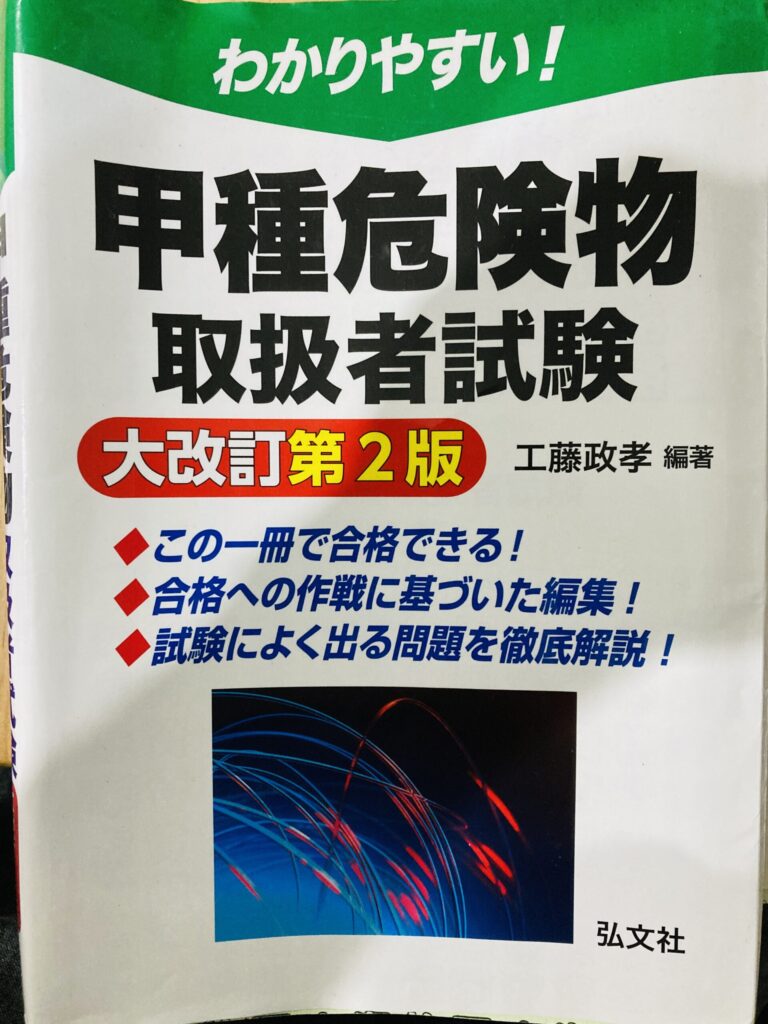
試験内容を詳細に網羅されているわけではありませんが、解説がわかやすく危険物取扱者で必要となる基礎的な理解を深めるために丁度良い一冊となっています。実務で調べ物をする際に、参考書としても使いやすいです。
2. 甲種 危険物取扱者試験 令和5年版
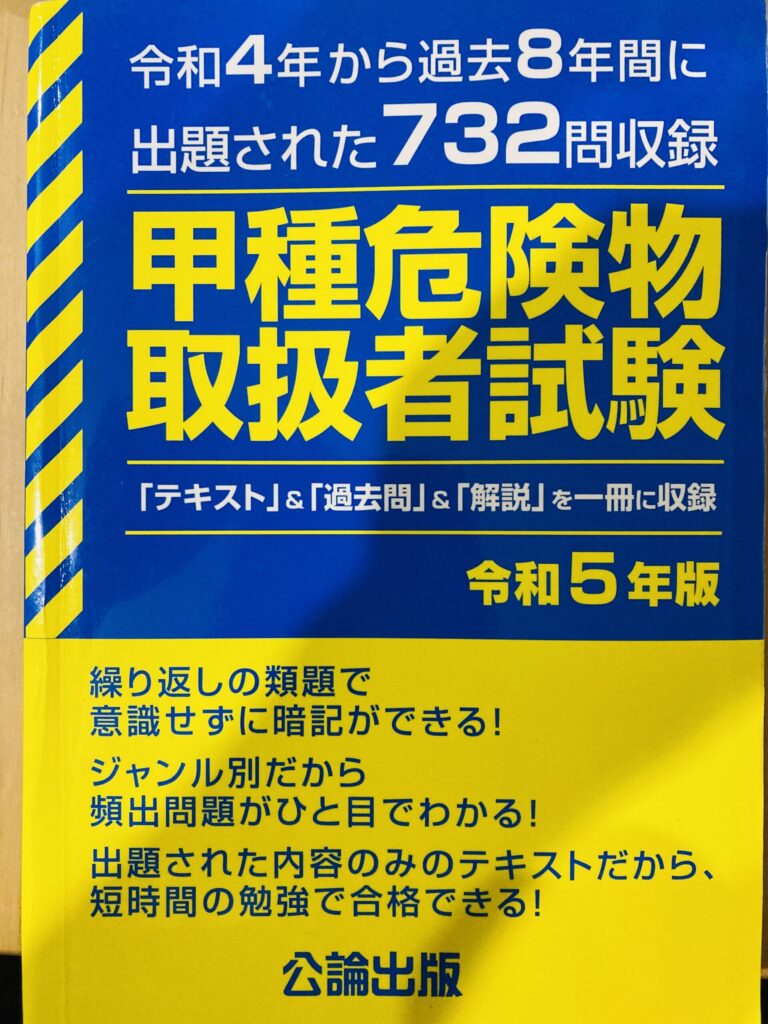
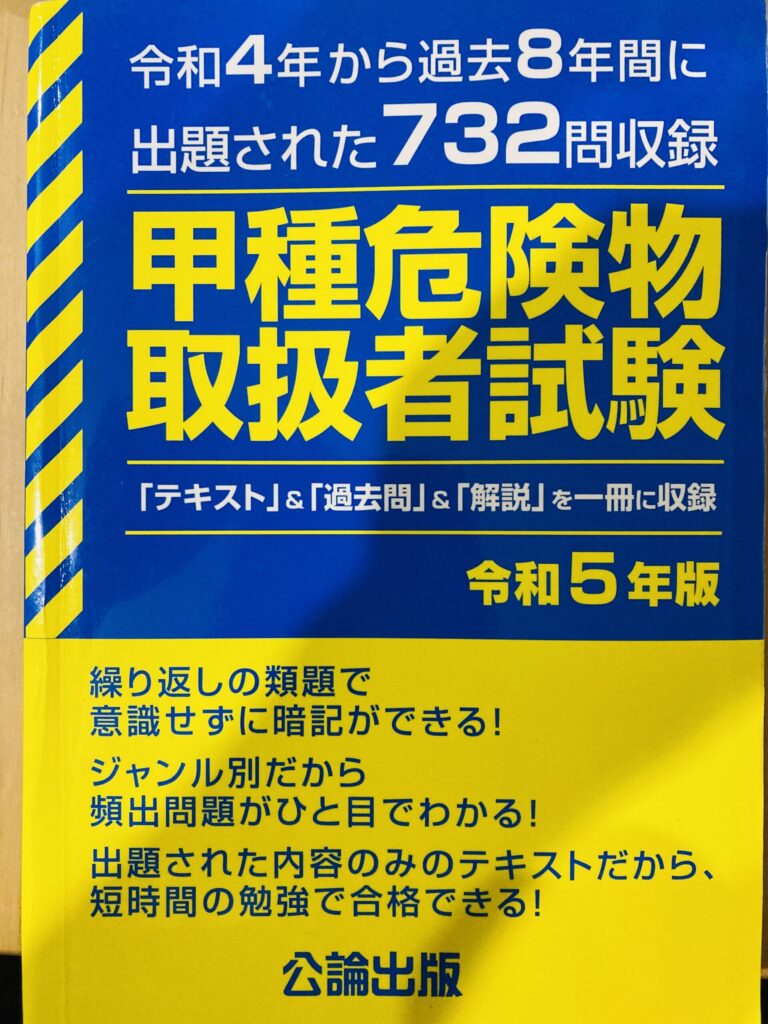
試験対策にはこの一冊があれば十分と言っても過言ではありません!勉強時間の8割は、この本で試験対策していました。ただし、各項目の解説が不十分に感じることもあるので、「わかりやすい!甲種危険物取扱者試験」も活用するとより効率的に理解が深まると思います。
3. ユーキャンの甲種 危険物取扱者
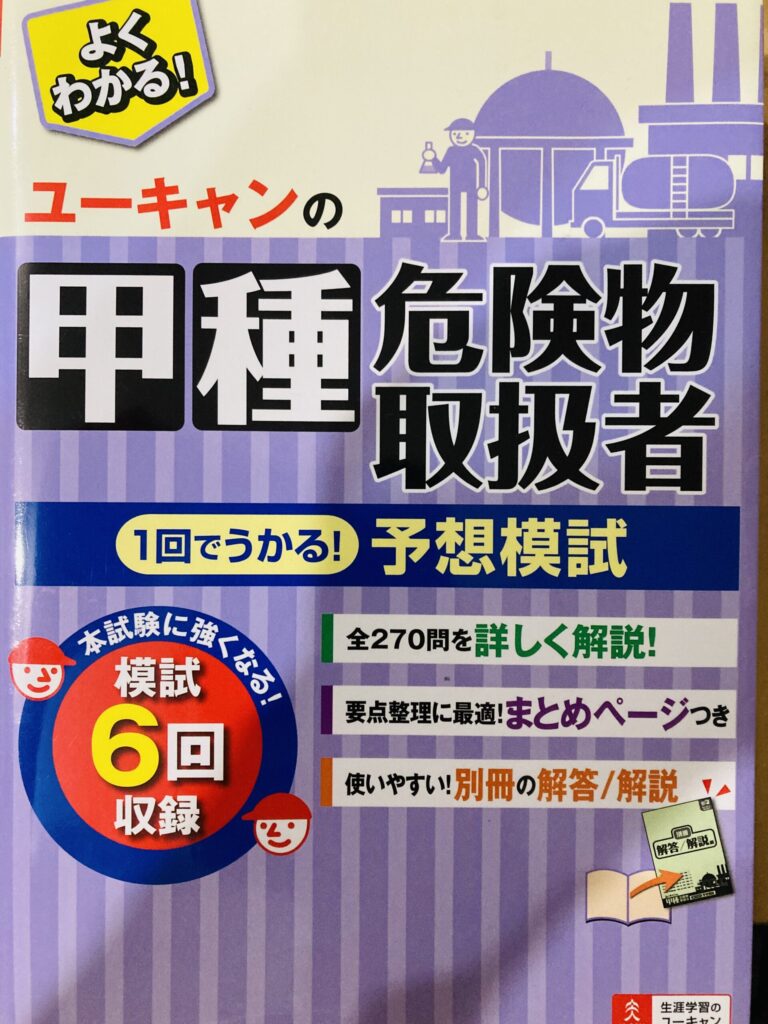
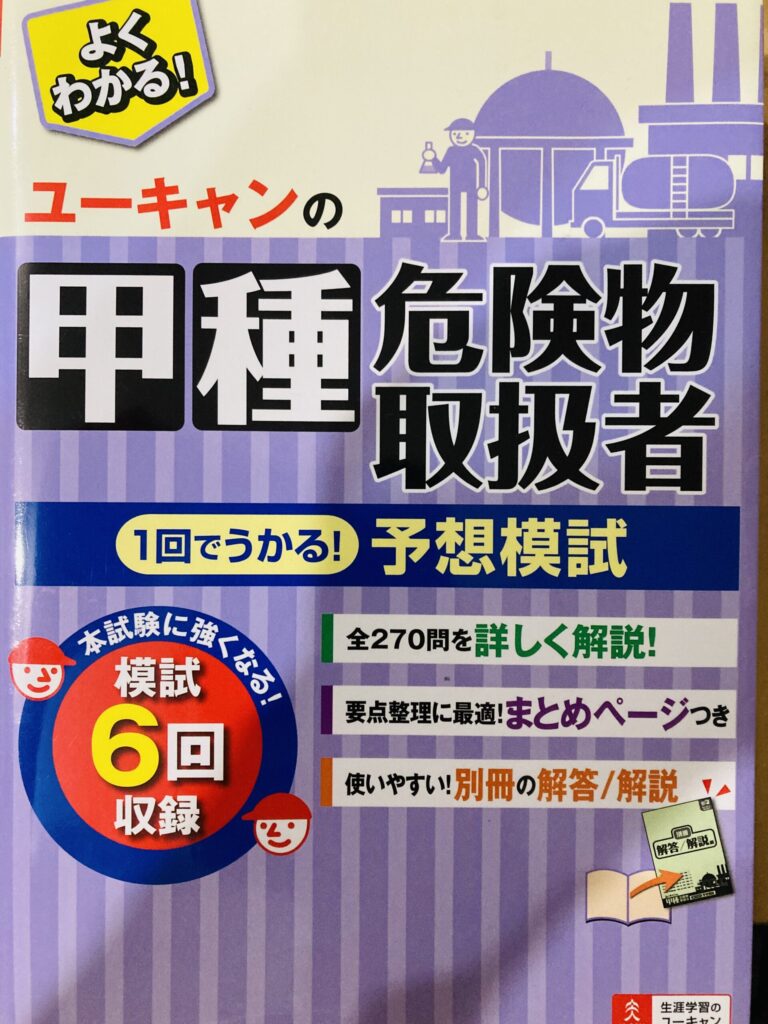
模擬テストが6回分収録されています。難易度は実際の試験よりも少し簡単なため、試験直前に自信を付けるのに良いかもしれません。
4. 本試験形式!甲種危険物取扱者 模擬テスト
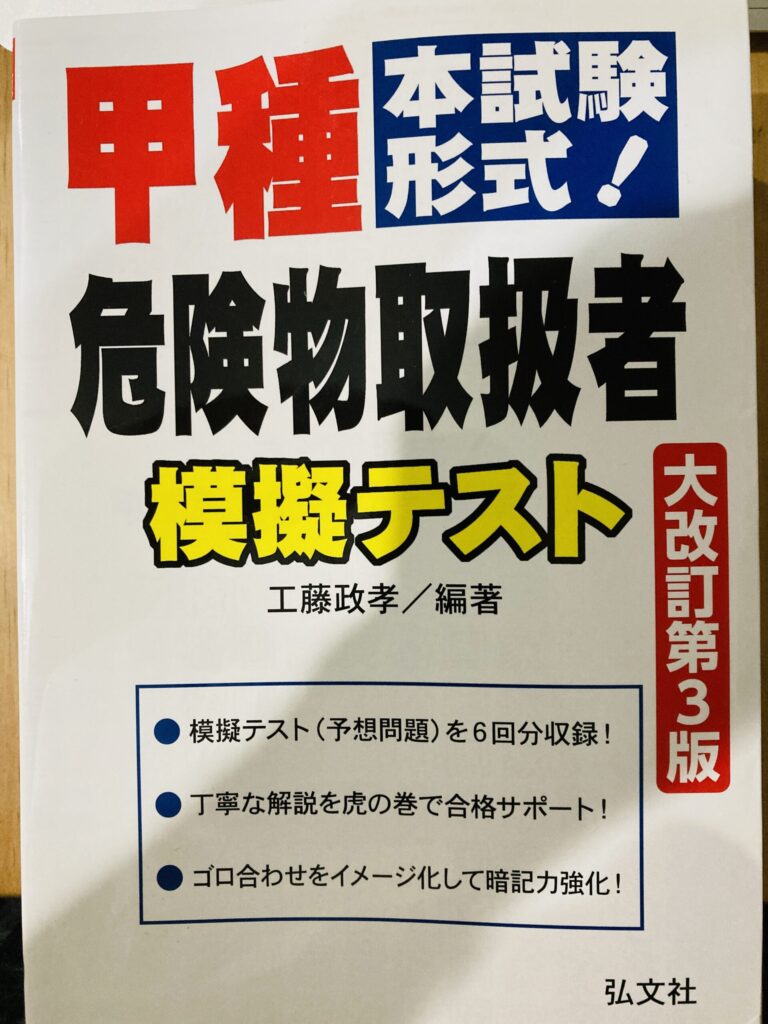
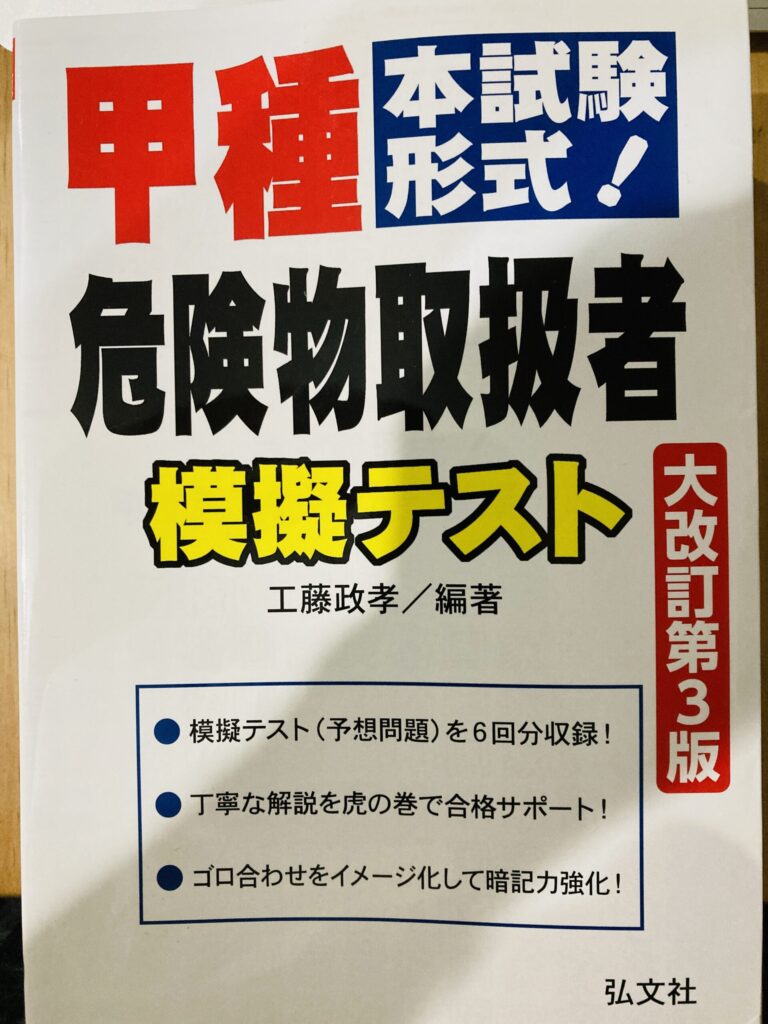
こちらも模擬テストが5回分収録されており、難易度は本試験に近いレベルに設定されています。巻末にある「合格大作戦〜虎の巻〜」は暗記しなければいけない項目がまとめられており、化合物の性状や法令の暗記に大変役立ちました
その他のおすすめ勉強法
上記で紹介した書籍の教材に他にも、YouTubeの解説動画もおすすめです。活字を読んでいると疲れるので、家事などをしながら流し聞きしていました。
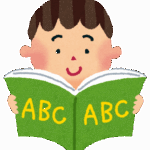
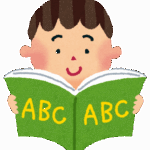
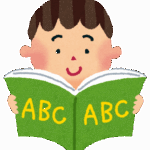
動画は1.5倍速〜2倍速でみるとより効率的に学習できるのでオススメです。
まとめ
危険物取扱者は幅広い業界で評価されている国家資格であり、その中でも甲種は最も価値の高い資格です。受験するためには一定の条件が必要となりますが、乙種を取得して実務経験のある方や、化学系の大学を卒業してキャリアアップを考えている方は、是非挑戦してみてください。いきなり甲種を受験するのが難しいという方には乙4種の受験がおすすめです。第4類の危険物にはガソリンやアルコールなど実用的な危険物が多く含まれており、資格としての需要が高いです。役に立つ資格を取りたいけど、何を取れば良いかわからない人もぜひ受験してみて下さい。

コメント